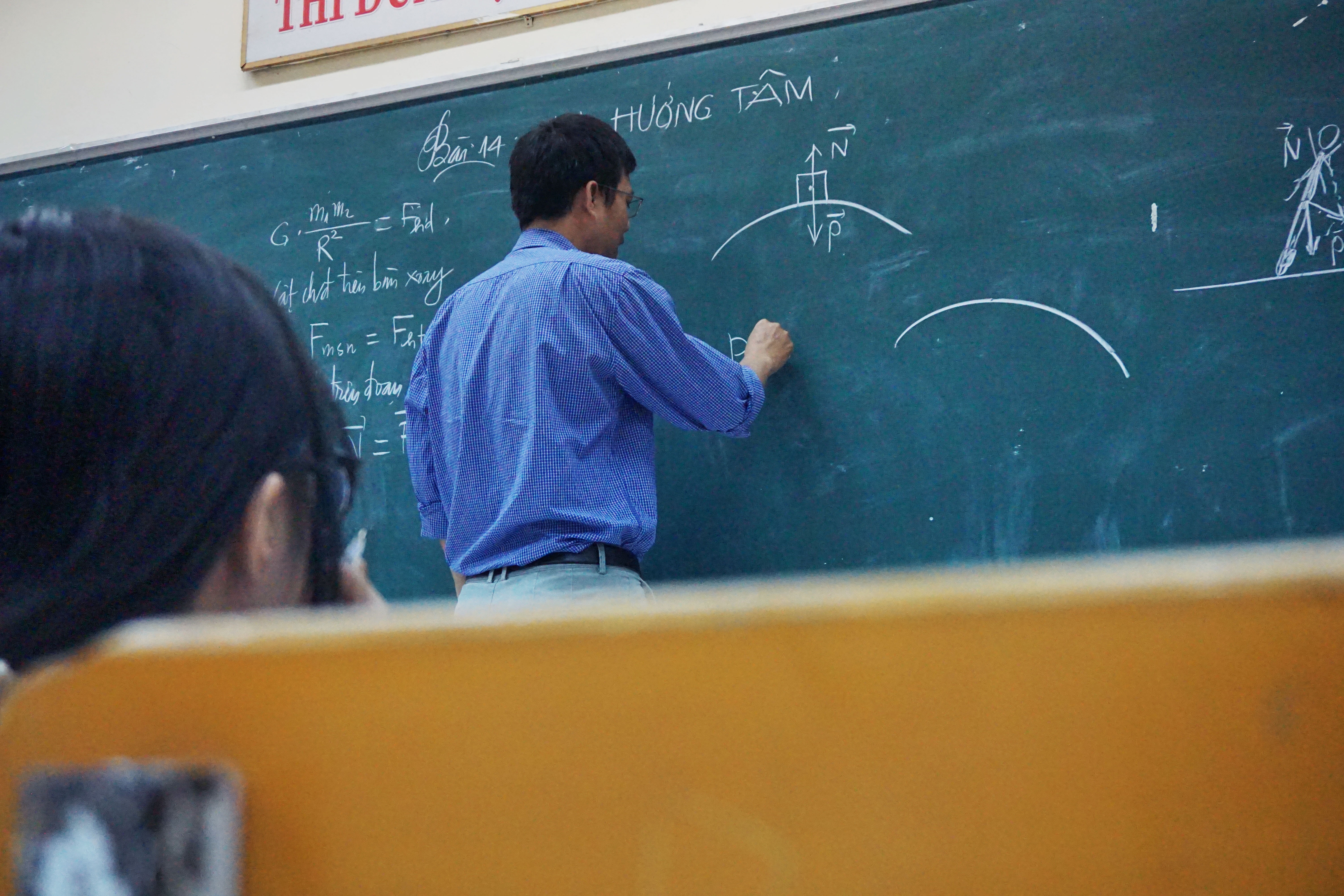
「なぜ、授業についていけないの?」
「なぜ、いつも忘れ物をしてしまうの?」
「なぜ、時間が守れないの?」
「なぜ、遅刻ばかりしてしまうの?」
「なぜ、宿題が全くできないの?」
学齢期になると様々な問題が発生します。
そもそも同じ文部科学省管轄でありながらも
幼稚園と小学校では、目的も制度も大きく異なります。
保育園と小学校であれば、その混乱は大きくて
当たり前です。
しかし、その制度の違いについての混乱も
「皆、対応できている」
「お宅のお子さんだけが出来ていない」
と回答する先生がいるようです。
皆ができることは、「できて当然!」という
考え方なんですねって感じです。
皆ができていることに「我が子」ができるかどうか、
ここは子を持つ全ての親が気になるところだと思います。
例えば、小学1年生だと
「授業中に座っていなければならない」
ということさえ、理解しきれなくて
授業中にウロウロしてしまう子もいるはずです。
まずは、誰もが思い付く「一般常識」に関して。
そもそも小学校に入って、初めて授業を受けているはずなのに
「授業は座って受けて当然!」
って、乱暴すぎだと思いませんか。
そして、「授業中は座っているもんだ」と聞いたとしても
「短期記憶」が低ければ、すぐに忘れてしまいます。
忘れてしまえば、行動是正は進みません。
そして、度々、同じことで注意を受けていると
「何度、言えば分かるんだ!」
となぜか、経ち歩いていることではなく
「回数」に関して怒られることになります。
何回って言われても、そんなことは分かりません。
そもそも、短期記憶自体、自分で操作しているわけではないですし。
生まれ持った「短期記憶が原因で忘れてしまう」というのが理由ですし。
全く理不尽な怒られ方になります。
また、周囲の状況を見渡すことができなければ、
他の生徒と同じ行動にはなりません。
目は、視界に入ったものを全て捕らえているわけではありません。
視界に入っていても「脳」がそれを認識していなければ
それは、見えていることにならないのです。
例えば、家の玄関や廊下に大きなゴミが落ちていました。
どう考えても絶対に視界に入る大きさです。
そのゴミについて「何でゴミを片付けないの?」と聞いても
「ゴミなんてあった?」
という具合いで返されてしまうのです。
「いやいや、どう考えても視界に入っているよね?」
と聞いたとしても、どうやら見えていないようなのです。
当然、嘘をついている様子もありません。
このように人は、「目」でものを見ているわけではないのです。
では、どこでものを見ているのか。
そうです。
それは、「脳」なのです。
「脳」がものを認識したときに人は「見えている」を判断するのです。
そして、その「脳」は過去に経験のあるものや興味があるものを
優先的にみる傾向があります。
だから、見た経験がないものや興味がないものは
正しく「目に入らない」のです。
皆さんも興味があることの情報は、色々入ってくると思いますが、
興味がないことの情報は、あまり入ってきませんよね。
同じものを見聞きしても、その人によって見聞きしているものが異なるのは
「興味があるかないか」の差なのです
我々、発達心理サポートセンターでは
その「目」に入ったものを認識できるかどうかを「視覚認知」と呼んでいます。
さて、学校の授業に話を戻します。
小学1年生の子で視覚認知が低い子は、
自分以外のクラスメイトが何をやっているかは
認識できていないことがあります。
これこそが、先ほど申した「視覚認知」なのです。
だから、他のクラスメイトが椅子に座って
先生の話を一生懸命に聞こうとしていも
それが分からないので、自分の興味が赴くままに
行動をしてしまうのです。
当然、その子に悪気はないのです。
しかも、皆、ちゃんと椅子に座って話しを聞いているのに
あなただけ何で皆と同じ行動ができないの?
と先生が言ったとしても、
その皆が誰を指しているのかも分からないし、
視覚には入っていても認識できていないので
全くもって先生の言い分は理解できないのです。
当然、そういった子は「場の空気」を読む力も
弱いはずです。
ちなみに皆さん、「場の空気」を読む力って
数値で表せるって知っていましたか?
WISC-㈿(ウィスク4)という検査で
「場の空気」を読む力が数値で出てきます。
興味がある方は、お問い合わせ下さい。
さて、「場の空気」が読めない子どもは
授業中の空気、先生が怒っているときの空気、
そういったものが理解できていないのです。
だから、授業中にふさわしくない言動をしたり、
先生が怒っているのにニヤニヤしたりして
怒られてしまうのです。
それらも全てその子に悪気はないのです。
ただ、少しだけ「場の空気」を読む力や
または「一般常識力」が弱いだけなのです。
なのに、一部の先生は烈火のごとく怒ったり、
親の躾の問題だ、なんて言ったりする。
全く理不尽ですよね。
さて、小学校に進学でして
もっとも大きな問題は「授業についていけない」です。
授業についていけない子どもは、一体どうなるのでしょうか。
そうです。
ご推察のように「不登校」になるのです。
実際に「不登校」になった子どもの中には
「授業についていけない」という理由を挙げた子どもが多数いました。
普通に会話が出来ている、考えもしっかりしている、
それなのになぜ、授業についていけないのか。
その理由をこの後で、詳しくご説明いたします。
そして、「忘れ物が多い」「時間が守れない」などについても
それぞれのページでご説明いたします。
・授業についていけない
・忘れ物が多い
・時間が守れない
・遅刻をしてしまう
・宿題ができない













